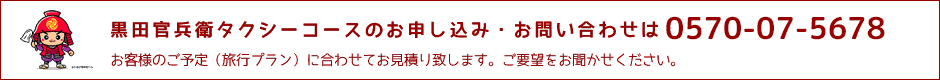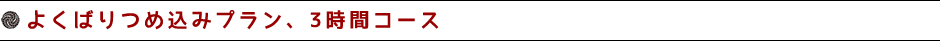
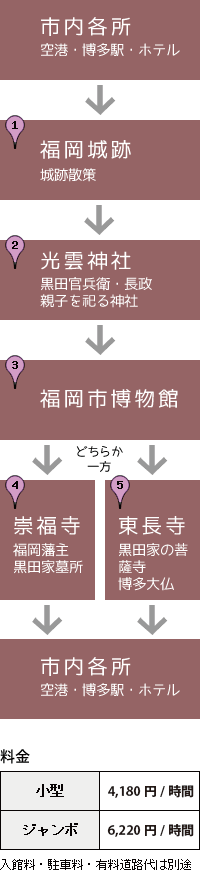
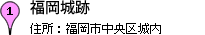
筑前52万3千石の領主となった初代福岡藩主・黒田長政が、慶長6年(1601)から7年がかりで築城しました。平山城で、大中小の各天守台と47の櫓(やぐら)があったようです。現在は多聞櫓(重要文化財)、(伝)潮見櫓、下之橋御門、祈念櫓、母里太兵衛邸長屋門、名島門などが保存され、大天守台は博多湾が一望できる展望台になっています。堀には県指定天然記念物のツクシオオガヤツリが自生し、城内には万葉歌碑もあります。国指定の史跡で、別名「舞鶴城」とも呼ばれていました。
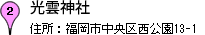
万葉の時代、荒津山と呼ばれた景勝の地が現在の西公園。黒田如水・長政を祭った光雲(てるも)神社や母里太兵衛と幕末の志士・平野国臣の銅像、加藤司書の歌碑、徳富蘇峰の詩碑、万葉歌碑など多くの先人の碑があります。展望台からは、東に福岡市街地、北に博多湾や海の中道、志賀島など見事な景観が一望できます。公園内には約1,300本の桜が植栽されており、春には多くの花見客で賑わう花見スポットです。
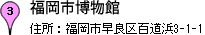
福岡タワーを背にして建つ、ハーフミラー貼りの博物館。常設展示室に国宝「金印」を所蔵。ここでしか買えない金印のレプリカは大人気のお土産グッズです。また、福岡生まれの現在でも動くものとしては国産最古の自動車も展示。他に企画展示をしている4つの部門別展示室と巡回展などを開催する特別展示室、アジア各国の楽器やおもちゃで遊べる体験学習室などさまざまな施設も設けられています。
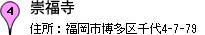
臨済宗大徳寺派(山号:横岳山)仁治元年(1240)、湛慧が大宰府横岳に創建する。翌年宋から帰国した聖一国師(円爾弁円)が招かれ開堂説法。文永9年(1272)に大応国師(南浦紹明)が入寺し開山となった。その門派に大徳寺開山宗峰妙超、妙心寺開山関山慧玄などの高僧を輩出した。慶長5年(1600)、黒田長政によって現在地に移転され。黒田家の菩提寺となる。福岡城本丸表御門を移した山門や、名島城の遺構と伝えられる唐門は県指定文化財(建造物)。
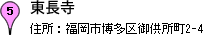
寺伝では大同元年(806)、唐から帰国した弘法大師の開基と伝えられる真言宗の古刹です。当初は海辺の地にあったようですが、福岡藩2代目藩主・黒田忠之によって現在の場所に移転。墓地には2代・忠之、3代・光之、8代・治高の墓がある黒田家の菩提寺となり、300石の寺領と山林15万坪の寄進がなされています。毎月28日には六角堂の扉が開き、中の6体の仏像が拝観できます。またここには、平成4年(1992)に完成した、木造座像としては日本最大の大きさを誇る「福岡大仏」があります。毎年2月の節分には多くの市民が集まり、賑わいを見せます。
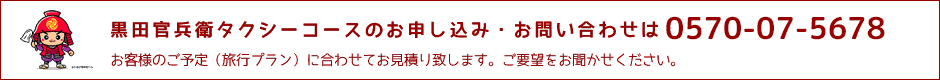
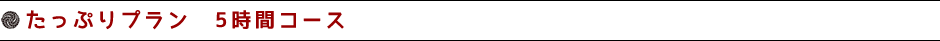
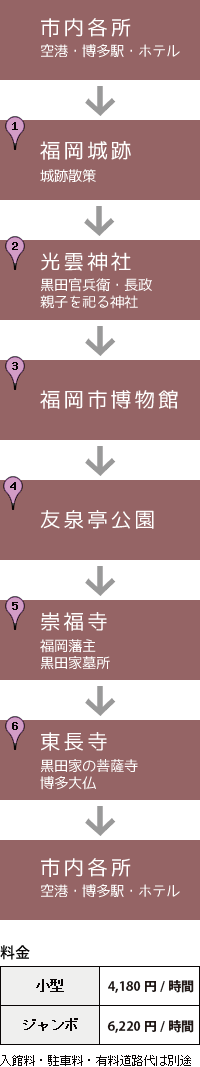
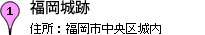
筑前52万3千石の領主となった初代福岡藩主・黒田長政が、慶長6年(1601)から7年がかりで築城しました。平山城で、大中小の各天守台と47の櫓(やぐら)があったようです。現在は多聞櫓(重要文化財)、(伝)潮見櫓、下之橋御門、祈念櫓、母里太兵衛邸長屋門、名島門などが保存され、大天守台は博多湾が一望できる展望台になっています。堀には県指定天然記念物のツクシオオガヤツリが自生し、城内には万葉歌碑もあります。国指定の史跡で、別名「舞鶴城」とも呼ばれていました。

万葉の時代、荒津山と呼ばれた景勝の地が現在の西公園。黒田如水・長政を祭った光雲(てるも)神社や母里太兵衛と幕末の志士・平野国臣の銅像、加藤司書の歌碑、徳富蘇峰の詩碑、万葉歌碑など多くの先人の碑があります。展望台からは、東に福岡市街地、北に博多湾や海の中道、志賀島など見事な景観が一望できます。公園内には約1,300本の桜が植栽されており、春には多くの花見客で賑わう花見スポットです。
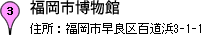
福岡タワーを背にして建つ、ハーフミラー貼りの博物館。常設展示室に国宝「金印」を所蔵。ここでしか買えない金印のレプリカは大人気のお土産グッズです。また、福岡生まれの現在でも動くものとしては国産最古の自動車も展示。他に企画展示をしている4つの部門別展示室と巡回展などを開催する特別展示室、アジア各国の楽器やおもちゃで遊べる体験学習室などさまざまな施設も設けられています。
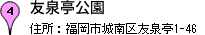
池泉回遊式の日本庭園が美しい友泉亭公園。もともとは、6代目福岡藩主・黒田継高(つぐたか)が旧早良郡田島村に建てた別荘。藩儒・竹田定直が撰んだ久世通夏(くぜみちなつ)卿の「世にたへぬあつさもしらずわき出る 泉を友とむすぶいほりは」という和歌からこの名が付けられました。西北に福岡城を望み、樋井川の流れと湧水を水源にしたという池泉や、中島を配した趣のある亭の様子が「筑前国続風土記附録」の絵図に描かれています。
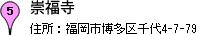
臨済宗大徳寺派(山号:横岳山)仁治元年(1240)、湛慧が大宰府横岳に創建する。翌年宋から帰国した聖一国師(円爾弁円)が招かれ開堂説法。文永9年(1272)に大応国師(南浦紹明)が入寺し開山となった。その門派に大徳寺開山宗峰妙超、妙心寺開山関山慧玄などの高僧を輩出した。慶長5年(1600)、黒田長政によって現在地に移転され。黒田家の菩提寺となる。福岡城本丸表御門を移した山門や、名島城の遺構と伝えられる唐門は県指定文化財(建造物)。
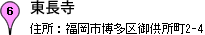
寺伝では大同元年(806)、唐から帰国した弘法大師の開基と伝えられる真言宗の古刹です。当初は海辺の地にあったようですが、福岡藩2代目藩主・黒田忠之によって現在の場所に移転。墓地には2代・忠之、3代・光之、8代・治高の墓がある黒田家の菩提寺となり、300石の寺領と山林15万坪の寄進がなされています。毎月28日には六角堂の扉が開き、中の6体の仏像が拝観できます。またここには、平成4年(1992)に完成した、木造座像としては日本最大の大きさを誇る「福岡大仏」があります。毎年2月の節分には多くの市民が集まり、賑わいを見せます。
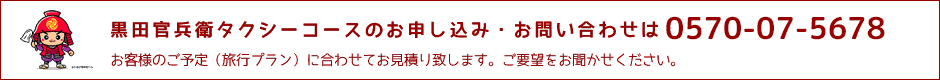
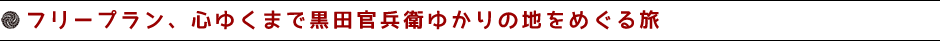
ご希望の黒田官兵衛ゆかりの地をご案内致します。
お客様の日程に合わせてプランを設定していただけます。ご要望をお聞かせください。
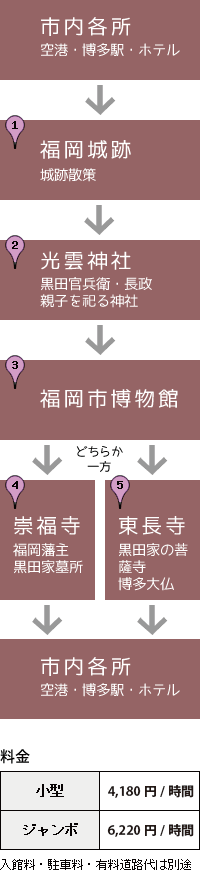
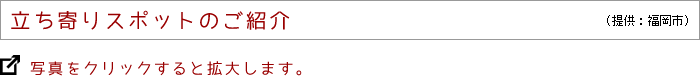
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
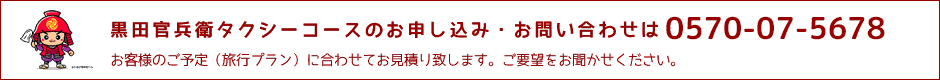
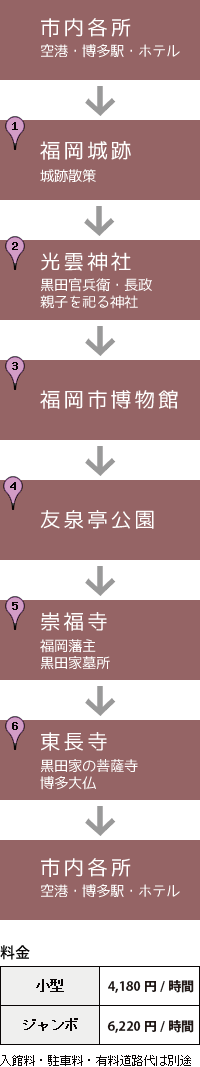
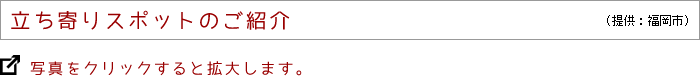
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
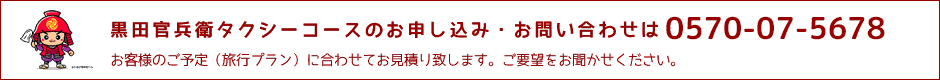
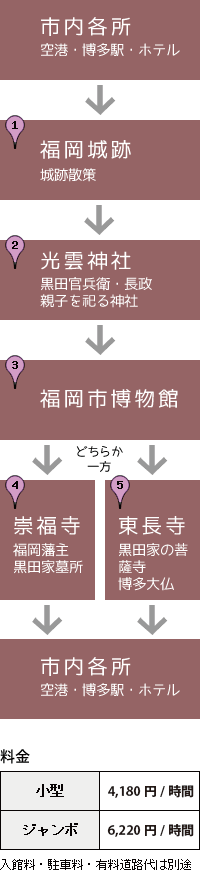
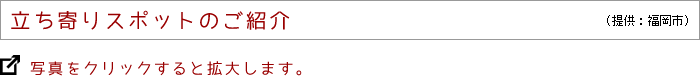
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
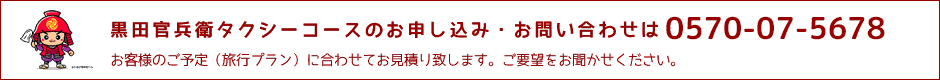
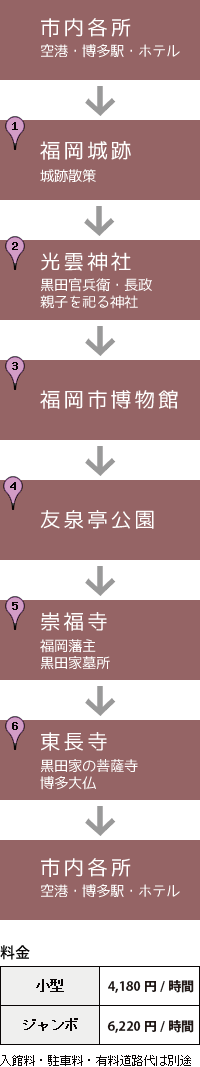
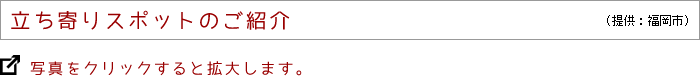
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()